※この記事は、この作品をこれから見る方へ向けた紹介&ちょこっと感想です。
予告や公式サイトでわかる程度の展開には触れていますが、映画の結末や重大な展開には触れていない、ネタバレなし感想になります。
どんな作品なのかを知りたい方は、ぜひご覧になってください。
この記事で、この映画に興味を持ってもらえたら嬉しいです。
映画『近畿地方のある場所について』の基本情報
『近畿地方のある場所について』(2025年/日本)
監督:白石晃士
原作:『近畿地方のある場所について』(背筋:著)
脚本:大石哲也、白石晃士
出演(キャスト):菅野美穂、赤楚衛二、ほか
→映画『近畿地方のある場所について』の公式サイトはこちら
白石晃士監督&モキュメンタリーホラー好きにおすすめ
・白石晃士監督作品が好き
「白石節(?)が炸裂している」と思うので、白石監督のコアなファンなら歓喜する展開かもしれません!
・モキュメンタリーホラーが好き
“本当に起きた出来事を見ている”感覚を味わえるので、リアル志向のホラー好きに向いています。
・原作小説ファン(単行本版/文庫版)
原作小説(単行本版)を楽しく読んだ方なら、映画の前半までは間違いなく楽しめます。
※文庫版は単行本版と内容が違うという噂なので、文庫版を読んだ方がどう思うかはわかりません。
キャストの魅力(赤楚衛二・菅野美穂・九十九黄助)
菅野美穂さん、赤楚衛二さんの演技は、じわじわとした怖さを感じられて、とても良かったです。
知る人ぞ知る、九十九黄助(つくも・きすけ)さんという俳優さんの出演も印象的でした。
ホラー映画が好きで、YouTubeで解説動画をよく見ている方なら、九十九さんをご存知なのではないでしょうか?
九十九さんの出演シーンは、怖いのにちょっとメタ的な笑いで「ふふっ」ってなるので、ファンの方にはぜひ見てほしいです。
モキュメンタリーホラーとは? 初心者向け解説
ドキュメンタリーのような手法を使って、リアルな恐怖を演出するホラーのことを指します。
擬似ドキュメンタリー、つまりドキュメンタリー風のフィクションです。
フェイク・ドキュメンタリーとも呼ばれます。
日本で有名になったのは、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999年)のヒットからではないかと思います。
【amazonプライム・ビデオ/レンタル・購入】
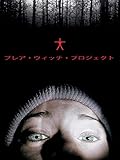
ブレア・ウィッチ・プロジェクト (字幕版)
『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、ファウンド・フッテージという手法を使った映画の代表的な作品です。
ファウンド・フッテージとは「発見された映像」という意味で、撮影者が行方不明になっていたり、誰が撮ったのかわからない映像を、“そのまま”公開した、という体裁をとる作品のこと。
この疑似ドキュメンタリー手法はホラーと相性が良く、白石晃士監督の『ノロイ』(2005年)もその代表例です。
『近畿地方のある場所について』あらすじ(ネタバレなし)
「私の友人が、行方不明になりました」
オカルト雑誌の特集記事のための資料まとめをしていた、編集長が失踪した。
部下の小沢(赤楚衛二)は、この特集を完成させられないと雑誌が廃刊になると聞き、失踪した編集長が手がけようとしていた記事を完成させるために、オカルトライター仲間の瀬野千紘(菅野美穂)に協力を求める。
編集長がどんな記事を書こうとしていたのか、詳しく知らない2人は、残されていた資料を確認していくことにする。
過去の未解決事件や、集団ヒステリーの映像、行方不明になった人物が最後にネットに残した動画など、さまざまな資料を調べていくうちに、それらがすべて「近畿地方」の、とある場所周辺で起こっていることがわかる。
そうして核心に近づいていく2人の周囲で、奇妙な出来事が起こり始めるが……
ちょこっと感想:前半はじわじわ怖い!
原作小説(単行本版)を読んだので、基本的なストーリーや、物語の伏線などは知っている状態で映画を見ました。
怖かったです。
前半までは。
「前半までは怖かった」というのは、別の言い方にすると、「前半までは原作に沿ったストーリーだった」、ということになると思います。
原作は、読んでて結構怖かったんですよ。
最初は関連がなさそうに見えた、雑多な現象や情報が、集まっていくにつれて、だんだんと輪郭がはっきりしてくる。
「あれ? これってさっきのと同じじゃない?」
「これって、シチュエーションは違うけど、同じ現象なんじゃないの?」
そうして、正体不明だった“怪異”の全体像が、少しずつはっきりしてきて、自分が真相に近づいていくのと同様に、“怪異”のほうからも、自分にどんどん近づいてくる……
そういう怖さを、原作小説に感じました。
ぞわぞわとした怖さを感じていたので、単行本版の巻末に袋とじされたおまけ(?)があったんですが、そのおまけを見ると呪われるような気がして、開封しませんでした。
なので、そこに何が書いてあったのか、私は知りません。
そんな感じで、原作は怖かった、という印象があるので、この映画を見るのを楽しみにしていました。
原作と映画の違い?
原作と映画で、冒頭から大きく違っている部分もあるんですが、ストーリーの展開としてはほぼ同じです。
・とあるオカルト案件を追っていたライターが行方不明になる
・その行方を探す&調べていた案件に何か手がかりがあるのではないかと、資料を追いかける
・それぞれ単発で起きた事件や情報に、偶然だとは思えない共通点があることに気づき始める
・証言者の周囲で奇妙なことが継続して起こっていたり、調査者にも奇妙なことが起こり始める
これ、文章で読んでいたときも怖かったけど、映像で見ると、怖さがくっきりすると思いました。
理解不能な動画がある、というのを文章で説明されるのも怖かったけど、それが実際に“動画”として映像化されてるわけですからね。
80年代風のテレビ映像や、最近の動画プラットフォームでのライブ映像。
その質感の違いなども伝わるので、本物の“記録映像”を見ているような気分になります。
映画館のスクリーンから目を離せず、じっと見つめているうちに、正体不明の“怖いもの”に近づかれているという感覚になって、いつのまにか指先が冷え切っている。
そうして固唾を飲んで物語を見つめていたら、途中からなんか違う感じになってきて、後半はちょっと個人的には「んん?」ってなったわけですが。
前半というか途中までは、“じわじわと怖くなっていく”という意味で、すごくよかったです。
まとめ:怖い映画を探しているならおすすめ
じわじわと怖くなっていく体験がしたかったり、白石監督のファンだったりするなら、映画『近畿地方のある場所について』の鑑賞をお勧めします。
個人的には、後半は「んんー?」って思ったんですが、前半の恐怖体験はすごくよかったと思うので、ぜひそれを体験してほしいです。
“白石監督のコアなファン”なら、後半は歓喜する展開のような気がします。
私は白石監督の作品を『サユリ』(2024)しか見たことがないんですが、それでも、「あ、これって白石監督作品のアレじゃない?」って思ったので。
それと、ひょっとしたら、文庫版の展開がこうなのかもしれません。
もしくは、映画版のために、独自の展開を用意していたのかも。
もしそうなのだとしたら、それは原作者の背筋さんの意向でそうなっているんじゃないかと思います。
怖い映画を見にいくのは、「怖いものを見たいから」です。
この映画の前半部分で、それは確実に叶えられます。
何を怖いと感じるかは人それぞれなので、最後まで怖く感じる人もいると思います。
なので、怖いものを見たい方は、ぜひ映画館でこの作品をご覧になってみてください。
【原作小説】近畿地方のある場所についての紹介
単行本版は読みましたが、2025年7月25日に発売された文庫版は読んでいません。
単行本版と内容が違うという噂なので、文庫版も読んでみようと思います。
※(1)となっていますが、1冊で完結です。
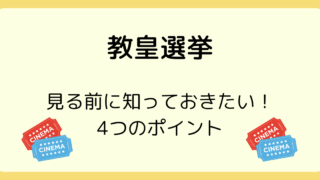
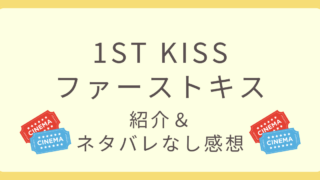
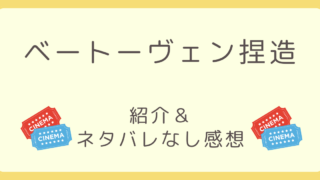
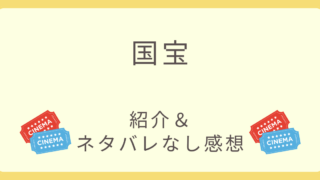
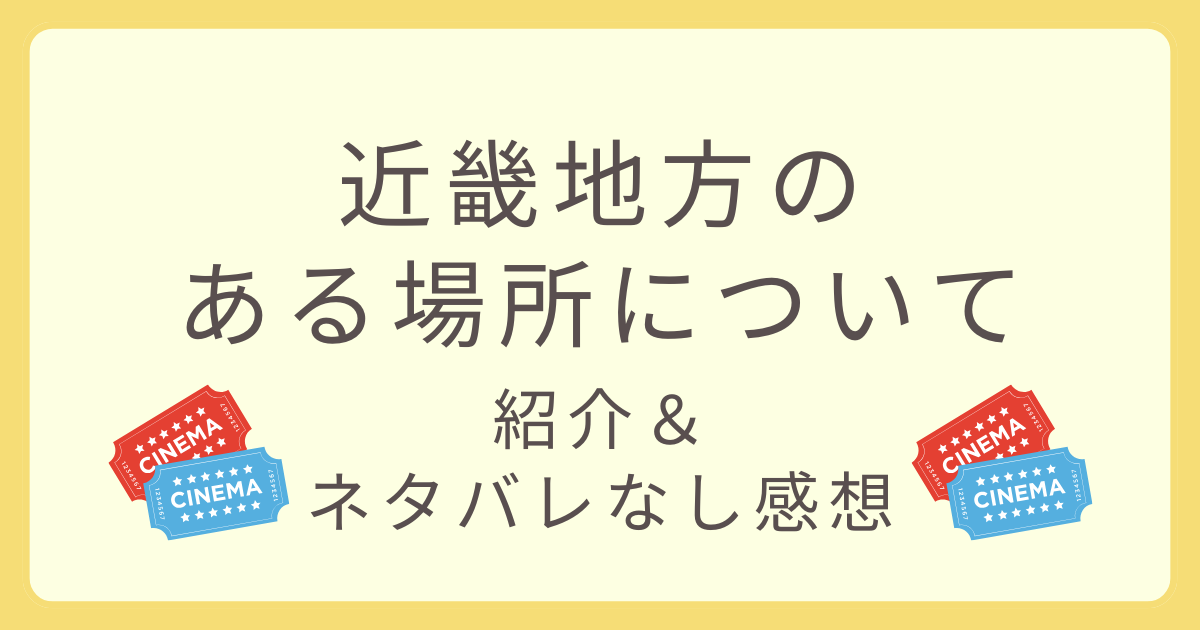
コメント