※この記事は、この作品を鑑賞した方へ向けた、結末までを明らかにしているネタバレ全開感想です。
ラストシーンにも思いきり触れています。
未鑑賞の方は、ご注意ください。
基本情報とあらすじ
基本情報
『異端者の家』(2024年/日本公開2025年/アメリカ・カナダ)
監督・脚本:スコット・ベック、ブライアン・ウッズ
出演:ヒュー・グラント、ソフィー・サッチャー、クロエ・イースト、ほか
→映画『異端者の家』の公式サイトはこちら
あらすじ
モルモン教(末日聖徒イエス・キリスト教会)の布教活動をしている2人の若い女性、シスター・バーンズ(ソフィー・サッチャー)とシスター・パクストン(クロエ・イースト)は、訪問先リストに載っていた、森に囲まれた一軒家を訪れる。
ドアを開けて出迎えてくれたのは、初老の男性リード(ヒュー・グラント)。
にこやかで穏やかな笑みを浮かべている彼を前にして、まだ一人も改宗できていない(布教しても、信者になってもらえていない)シスター・パクストンは、布教の際に伝えているマニュアルのような勧誘の言葉をまくしたててしまう。
そんなシスター・パクストンにも嫌な顔をせず、家の中でもっと詳しい話を聞きたい、と言うリードに、2人は躊躇するそぶりを見せる。
たとえ布教のためであっても、自分と同性の住人が存在せず異性しかいない場合は、家に入ることはできないという決まりになっているのだ。
そのことを説明すると、「妻は今パイを焼いていて手が離せないから(玄関に)出てこれないが、じきにパイも焼きあがる。よければ一緒にパイを食べながら、妻と私に話を聞かせてもらえないか」とリードはにこやかに告げる。
そういうことなら、と2人は家の中に入ることを承諾し、リビング(応接室)へ案内される。
パイを焼いている香りが漂ってくる中、ローテーブルを挟んで向き合ったリードと2人のシスターは、モルモン教の教義についての話を始めるが……
感想
「信じる」とはなにか?
この映画の主題を一言で言うと、「信仰とは何か?」かなーと思います。
もっと簡単に言うと、「信じるとはどういうことか?」ですかね。
人が何か(この場合は宗教、神という存在)を信じるとき、何を根拠にして“信じる”のか?
信じる根拠を揺るがされたとき、人はどうするか?
信仰を捨てるのか?
それとも、信じ続けるのか?
信じ続ける場合、その根拠となるものは何か?
そういう、「信じる心」の本質を追求していくような会話が、リードと2人のシスターの間で交わされます。
リードは当初、「たったひとつの、本物の宗教とは何か? それを私は探している」と言っていました。
それで2人にいろいろなことを問いかけ、自分の宗教観についても話します。
リードの問いかけと、シスターたちの反応
ただそれだけなら、宗教問答、意見交換で済むんですが、リードの真の目的は別にありました。
それは、「信仰(何かを信じる)とは、支配である」ということを、彼女たちに体感・実感させるということです。
そのために彼女たちは、信仰心を揺るがすような問い詰めをされたり、家に閉じ込められたり、悲惨な光景を目の当たりにさせられたり、辛い思いをしたり、身体的に痛い目にあったり、という災難に見舞われることになるのです。
彼女たちが信仰しているのは、モルモン教(末日聖徒イエス・キリスト教会)と呼ばれる、キリスト教系の新宗教です。
1830年に創設されたそうです。
ジョセフ・スミスという創始者が、神からの啓示を受け、それを預言書にまとめたものをモルモン書、というらしいです。
キリスト教の三位一体を否定していることや、厳しい戒律があること、魔法の下着という独特の下着を身につけていることなどで有名です。
厳しい戒律によって、飲酒だけでなく、カフェインの摂取も禁じられています。
紅茶もコーヒーも緑茶も飲めないなんて、私には無理だなと思いました。
モルモン教の成り立ちと、一夫多妻制度の変遷
神からの啓示、言葉を受けた人を“預言者”といいます。
ジョセフ・スミスは神の言葉を聞いたと、自分は預言者だと言って、モルモン教を創始したわけです。
ちなみに、ジョセフ・スミスは当初、神からの啓示として、一夫多妻を主張し、実践していたそうです。
それは子供を多く産んで信者を増やすためでもあったそうですが、この一夫多妻制度が、のちにアメリカで問題視されました。
このことが原因でモルモン教の布教が禁止されそうになると、モルモン教の指導者は次のように言いました。
「神から、アメリカの法律に従うようにという言葉を預かった(=これが「預言」です)。一夫多妻制度はやめて、アメリカの法律に従い、一夫一妻とします」
このエピソードを聞くと、普段はあまり宗教のことを考えない日本人は特に、こう思うんじゃないでしょうか?
それ本当に神の言葉なの?
ただ自分(ジョセフ)が好色なだけだったんじゃないの?
それを正当化するために、一夫多妻制にするようにという神のお告げがあった、と言ったんじゃないの?
と。
宗教の正当性を問うリードの主張
リードもまさに、この点を彼女たちに問いかけます。
しかし彼女たちは、モルモン教信者にとっての預言者であるジョセフの言葉を信じているので、こう答えます。
「最初は一夫多妻という啓示を与えたけれど、アメリカの法律に違反するのは良くないからと、信者を救済するために、あらたな啓示があったんでしょう」
外部から見たら、それ明らかにおかしなこと言ってるよね、という事実を突きつけられても、彼女たちの信仰は揺らぎません。
そんな2人に、リードはさらに問いかけます。
「彼が言っている“神の言葉”を、君たちは信じているね。だが、彼が本当に神の言葉を聞いたのか、神の啓示を受けたのかは、誰にも証明できない。適当なことを言っているだけかもしれない。それなのに、なぜ君たちは彼の言葉を信じるのか?」
この問いに、シスター・パクストンは少し首を傾げながらも答えます。
「真実を言っていると、感じるから?」
真実を言っていると、自分がそう感じるから、信じる。
つまりこれは、「人は自分の信じたいものを信じる」ということです。
それが“真実”であるかは重要ではないんです。
そんなことはどうでもいい。
信じたいから、信じる。
これは、自分に都合のいいことだけを信じてしまう、それが真実だと思ってしまうという、危うい一面も指し示しています。
信じたいものを信じる、ということは、信じたくないものは事実や真実であっても信じない、ということだからです。
ブルーベリーパイの香りの正体
ブルーベリーパイのいい香りが漂うリビング、というより応接室ですかね、そこでリードと2人のシスターは宗教問答のような会話を続けます。
モルモン教を布教したい一心のシスター・パクストンですが、リードが宗教観についてどんどん詰めてくることに戸惑います。
リードは「君たちの信じている宗教は本物か? それはどうやって証明するのか?」と理詰めしてくるからです。
何か変だ、と不穏さを感じ、「そろそろ奥さんを紹介してもらえませんか?」と切り出すと、リードはにこやかに「パイの焼き上がり具合を見てくるよ」と部屋を出ていきます。
部屋に残された2人は、テーブルの上で灯されていたアロマキャンドルを何気なく確認します。
するとそこには、“ブルーベリーパイ”と書かれたラベルが貼ってありました。
2人は顔を見合わせます。
ブルーベリーパイを焼いているというのは嘘で、部屋に漂う香りはアロマだったのです。
この時点で、2人はリードが嘘をついていることに気づきます。
「妻がブルーベリーパイを焼いている」
ブルーベリーパイは焼いていないし、おそらく妻も存在しない。
騙された、と気づいた2人は玄関から出ようとしますが、内側から鍵を開けることができず、出ていけません。
そうして家に閉じ込められてしまった彼女たちは、逃げることもできず、リードの仕掛けた罠にはまっていくことになります。
宗教と信仰を問う会話劇の面白さ
リードの目的は「宗教とは、支配である」と彼女たちに認めさせることです。
認めさせるというか、理解してもらう、ということですね。
ただ説明を聞くだけでは、真に理解はできません。
「そういうことか」と自分で信じるに足る根拠を見つけ、腹落ちすることで、信じるようになる。
その過程を経なければ、理解したとは言えません。
なのでリードは、彼女たちが“自分で真実(リードの用意したもの)に気づく”ように、状況を悪化させ、追い詰めていくのです。
その、罠に嵌められ、状況がどんどん悪化し、追い詰められていく様子がホラーなんですが、メインは会話劇で、その会話がとても興味深かったです。
バージョンが違うだけの、同じもの
「宗教に限らず、いろいろなものが反復されている。違うものだと思っていても、実はバージョンが違うだけで、すべて同じものが単に反復されているだけなんだ」という話をリードは語ります。
“地主ゲーム”というものが開発され、それを他の人が勝手に“モノポリー”と新しい名前を付けてオリジナルゲームとして販売した。
地主ゲームはあまり知られないままだったが、モノポリーは全世界でヒットした。
そして今、モノポリーにはさまざまなバージョンが存在する。
これを宗教に当てはめると、一神教のユダヤ教、キリスト教、イスラム教でまったく同じ説明ができます。
ユダヤ人だけが信じていたユダヤ教。
ユダヤ教徒であったイエス・キリストが神から預言を受け、それを広めたのがキリスト教。
ユダヤ人しか信仰できないユダヤ教と違い、キリスト教は誰でも信仰できます。
そして、新たな預言者ムハンマドが神からの預言を受けて創始したのが、イスラム教です。
この3つの宗教の神は、ヤハウェとか父なる神とかアッラーとか呼ばれますが、同一の神です。
呼び名が違うだけで、信じている神は同じなんです。
つまり、一部の人しか知らなかった地主ゲームが、ユダヤ教。
それをわかりやすく世界に広めたモノポリーが、キリスト教。
さらに新しいバージョンとして登場してきた最新版モノポリーが、イスラム教。
この文脈でモルモン教を語るなら、モルモン教は世界に広がったモノポリー(キリスト教)の風変わりなスピンオフだと言えるのです。
証明不可能問題
リードのこういう説明は非常にわかりやすく、かつ興味深くてすごく面白かったです。
これらの宗教を信じている人たちは「そうかもしれないけど、そうじゃない!」と反発するかもしれませんが、私はここで挙がっている宗教の信者ではないので、ただひたすら「面白い、すごく面白いことを話している」と興奮していました。
リードの話や問いかけに、シスター2人は根拠のある反論ができません。
「君たちが信じている“風変わりなスピンオフ”が、唯一の本物の宗教だと、証明できるか? できないだろう?」と問い詰められているわけです。
もっとも、モルモン教に限らず、すべての宗教は、本物かどうかや、神の存在を証明することはできません。
これは長年、宗教学者や科学者が論争を繰り広げていることで、神の実在も不在も、どちらも証明できないのです。
そしてそれを、もちろん彼女たちも知っていました。
映画の後半は、会話劇ではなく、シスターたちの恐怖体験(痛い)の描写になっていくのですが、それも目的は「信仰とは、支配である」ことを“理解させる”ための演出です。
その過程で、シスター・バーンズはリードに殺されてしまいます。
一人になったシスター・パクストンは、リードの用意した“演出”により、「信仰とは、支配である」という結論に達します。
しかし、彼女はわかっていました。
その結論に辿り着くように、自分がリードに誘導されていたのだということを。
誰にも否定できない“本物”
信仰や、何かを信じることには、意味がないかもしれない。
なぜなら、信じるに足る、揺るぎない根拠というものが存在しないから。
それを認めたうえで、シスター・パクストンは言います。
「宗教において、“祈り”が何の効力もないことを知っている。
重病患者に対する、そういう実験があったから。
“祈り”を捧げられた人々と、“祈り”が捧げられなかった人々で、病気の治癒や死亡率に差はなかった。
祈りには、奇跡を起こす効果はない。
それでも、誰かのために祈る姿は美しい。
たとえ、何の効果もなかったとしても」
このシスター・パクストンの言葉は、すごくグッときました。
その通りです。
誰かのために祈ったり、願ったりしても、効果はないかもしれない。
だけど、誰かのために本気で祈ること、何かを心から願うこと。
それはとても美しく、尊い、まぎれもない本物の気持ちですよね。
この“本物”だけは、誰にも否定はできません。
それでも、信じることをやめない
リードに刺され、とどめをさされる寸前だったところを、死んだはずのシスター・バーンズに助けられ、シスター・パクストンは瀕死の状態で家を脱出します。
このシスター・バーンズの復活は、キリスト教におけるイエス・キリストの復活をなぞらえているんだろうなと思います。
シスター・バーンズは確かに死んだ。
その彼女が、シスター・パクストンを救済するために、復活し、そして再び死者となった。
シスター・パクストンは瀕死の状態だったので、もしかしたら、この復活自体が、彼女の見た幻想、妄想だった可能性はあります。
それでも、信じることをやめなかった彼女に起きたことは、“奇蹟”だったのかな、と思います。
映画のラスト、家を脱出し、携帯の電波が届くところにたどり着いたシスター・パクストンに、一匹の蝶が近づいてきます。
蝶に気づいたシスター・パクストンは、蝶の前にそっと手を差し出します。
幻想的なラストシーン
リードの家に向かう道中で、シスター・パクストンはシスター・バーンズに、こう言っていました。
「私は死んだら、蝶になりたい。
蝶になって、親しい人の指に止まりたい。
頭や、他の部位じゃダメ。
指先に止まることで、その蝶が私だって、その人に気づいてもらうの」
シスター・パクストンが差し出した手の指先に、そっと止まった蝶。
この蝶は、死んでしまったシスター・バーンズなのか。
それとも、この話をしていたのはシスター・パクストンなのだから、実は彼女は逃げ出したものの力尽きてしまい、蝶となって誰かの指に止まった、という演出なのか。
真実はわかりませんが、シスター・パクストンの震える指にそっと止まった蝶と、それを見つめるシスター・パクストンの姿は、とても幻想的で美しかったです。
何が真実か、わからない。
だけど、人は信じたいものを信じる。
私は、シスター・パクストンは助かって、指に止まった蝶はシスター・バーンズがお別れの挨拶に来た姿なんだと、信じます。
このシーンで映画は終わったので、すんごく痛そうな描写があるために、なかなか人におすすめしにくいけど、面白くていい映画だったな、と思いました。
面白いけど、共感性の高い人にはおすすめできない
ちなみに、この映画の「すんごく痛そうな表現」ですが、「想像できる痛み」なので、なかなか厳しいものがあります。
R15レーティングは伊達ではありません。
鈍器で殴られたり銃で撃たれたり、というのって、実は痛みをあまり想像できない気がします。
特に銃は、撃たれたことないので、想像するのに限界があります。
でもそれが、ナイフで皮膚を切る、という描写だったら?
何かで皮膚を切ってしまうって、日常でたまに起こりますよね。
カッターナイフで指先を切ってしまった、包丁で、ハサミで、もしくはただの紙きれで。
R15の痛みの表現は、もちろんそんなものとは比較にならないわけですが、あの何十倍、何百倍も痛いんだろうなということは想像できる。
そういう、“想像できる痛さ”の表現が多かったので、共感性が高い人はこの映画見れないな、と思いました。
この感想で紹介した以外にも、面白い会話がたくさんありました。
会話の内容とラストの展開については話しましたが、その他の細かい点については省略しています。
リードがどのように「信仰とは、支配である」とシスター・パクストンを誘導したのかなどは、説明していません。
その過程を知りたい方や、共感性そんなに高くないし痛い表現多分大丈夫という方は、機会があったらご覧になってみてください。
あと、映画の内容とは全然関係ないんですが、シスター2人がリードの家に入ったとき、応接室に「若い頃のリードが笑顔で犬と一緒に芝生に座っている写真」が一瞬映るんですけど、その写真のリード(ヒュー・グラント)がめちゃくちゃかっこよかったです。
【めちゃくちゃかっこいい若い頃のヒュー・グラントの出演作】
『ノッティングヒルの恋人』
『ラブ・アクチュアリー』
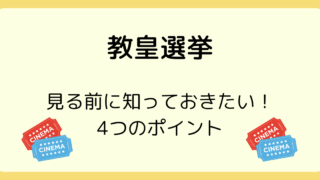
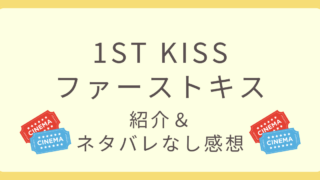
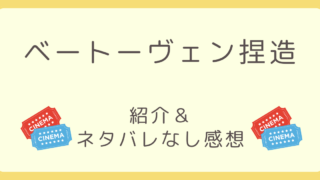
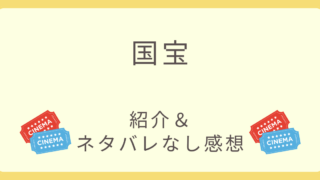
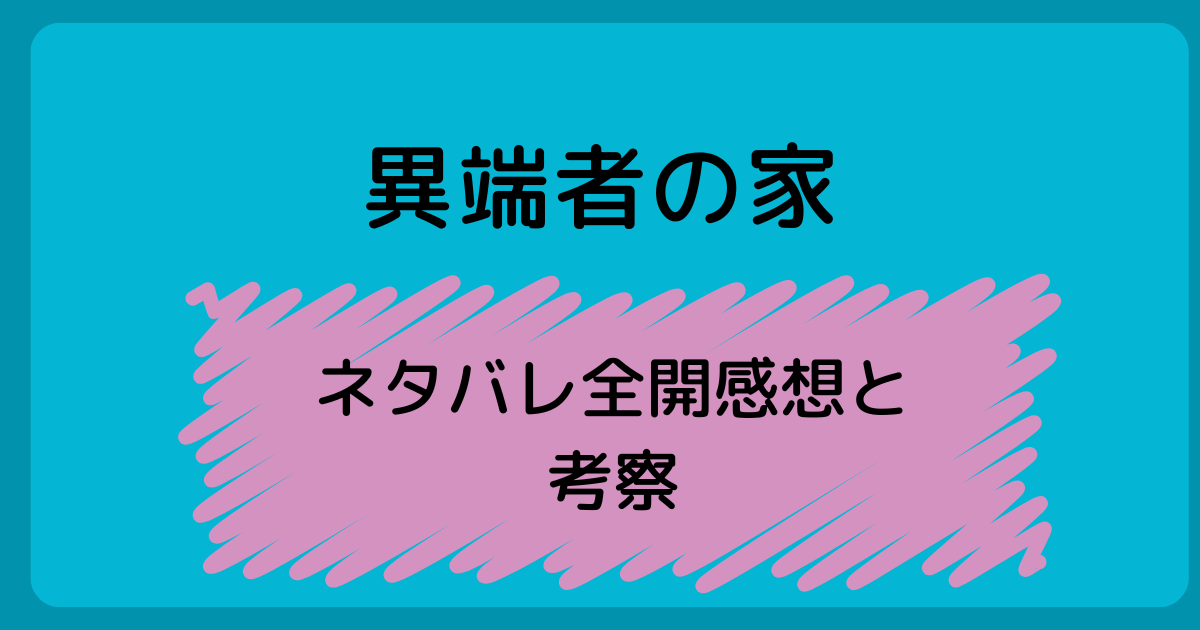
コメント
映画『異端者の家』のネタバレを読んで、信仰とは「祈ること」なのだと思いました。
私自身、信仰心は強くないのですが、毎日家族の健康や野良猫たちの幸せを願って、仏壇に手を合わせています😊
制度や宗教ではなくても、誰かを想い、祈るという行為そのものが信仰なのかもしれません。
この映画を通して、そんな気づきをもらいました。
日本人には「祈る」「願う」というのが、宗教とは別に当たり前の習慣になっていますもんね。
毎日手を合わせているのは、とても意味のあることだと思います!
この映画、ジャンルとしてはホラーなんですけど、そこからこんな気づきがあるのが、映画のいいところだなと思います。