※この記事は、この作品をこれから見る方へ向けた紹介&ちょこっと感想です。
予告や公式サイトでわかる程度の展開には触れていますが、映画の結末や重大な展開には触れていない、ネタバレなし感想になります。
どんな作品なのかを知りたい方は、ぜひご覧になってください。
この記事で、この映画に興味を持ってもらえたら嬉しいです。
※ベートーヴェンを知らない人でもOK!
歴史ミステリーとして楽しめます。
映画『ベートーヴェン捏造』の基本情報|公開日・キャスト
『ベートーヴェン捏造』(2025年9月12日公開/日本)
原作:小説(歴史ノンフィクション)『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』かげはら史帆・著(河出文庫)
監督:関和亮
脚本:バカリズム
テーマ曲演奏:清塚信也
キャスト:山田裕貴、古田新太、染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、生瀬勝久、小手伸也、野間口徹、遠藤憲一、藤澤涼架、ほか
上映時間:115分
配給:松竹
→上映館などを調べたい方は、映画『ベートーヴェン捏造』の公式サイトへどうぞ
映画『ベートーヴェン捏造』のあらすじ(ネタバレなし)
偉大な音楽家ベートーヴェンを伝説たらしめている逸話の数々は、秘書シンドラーによる捏造だった!?
偉大な作曲家ベートーヴェン(古田新太)に憧れて、ウィーンにやってきた青年シンドラー(山田裕貴)は、ある日憧れのベートーヴェンと会うことに成功する。
実際に会ったベートーヴェンは、シンドラーのイメージしていた姿とはかけ離れた、“小汚くてわがままなおっさん”だった。
しかし彼の音楽の才能が本物であることは明らかで、シンドラーはあっというまに実物のベートーヴェンに心酔してしまう。
ベートーヴェンの秘書となり、身の回りの世話をするようになったシンドラーは、偉大な作曲家ベートーヴェンのために、奔走するのだが……
映画『ベートーヴェン捏造』を見たいと思った理由
この映画の予告を見たとき、思いました。
「なんでドイツ人を日本人が演じているの?」
日本人がローマ人を演じるという『テルマエ・ロマエ』という作品もありますし、外国人の役を日本人が演じるということは、別におかしくはないです。
だけど、お馴染みの日本の役者さんたちが、ドイツ風の衣装を纏い、ドイツ名で呼ばれ、なのに日本語を話しているというのが、絵面としてめちゃくちゃ面白く、すごく興味を惹かれました。
その後、原作が日本の小説というか歴史ノンフィクションであると知って、だから全員日本人が演じるのか、と納得しました。
私はベートーヴェンの音楽が大好きなので、この映画すごく楽しく見られるんじゃないか?
というか、古田新太さんのベートーヴェンが、あまりにもベートーヴェンすぎる。
と思って見に行ったら、とても面白かったです。
原作の歴史ノンフィクションである『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』を読んでから、映画を見に行きました。
この映画を見るために、原作をまず読んでみた、という感じです。
原作を読んでからの映画は、なるほどこういう切り口にするのか~、という面白さがあったので、原作→映画という順番で見ると楽しいと思います。

Q:原作を読んでいなくても楽しめますか?

A:はい、映画だけでも十分理解できます!

Q:ベートーヴェンのこと、よく知らなくても大丈夫?

A:大丈夫です! 見どころを紹介します!
映画『ベートーヴェン捏造』の見どころ
日本人キャストがドイツ人を演じている面白さ
もうこれだけで十分面白いんじゃないかと思います。
お馴染みの俳優さんたちが「ベートーヴェン」「シンドラー」「カール」「ヨハン」などと呼ばれていることにおかしみを感じますが、そのうち気にならなくなりますし、むしろその違和感が、だんだん作品の味わいに変わっていきます。
それと、外国名が違和感ない人が数名いるのも面白いです。
たとえば、古田新太さん演じるベートーヴェン。
古田新太さんがあまりにも“ベートーヴェン”のため、彼がベートーヴェンと呼ばれていても、なんの違和感もありません。
演技力のなせるわざなのか、作り込まれた外見のなせるわざなのか。
古田新太さんのベートーヴェンは、必見です。
SNSがない時代の“情報戦”ー19世紀のレスバ!?
SNSがない時代でも、人は同じことをしているんだな。
と実感するところも、すごく面白いです。
X(Twitter)や他のSNS上で交わされる“レスバトル”が、当時は新聞の記事やコラム、本の出版という形で繰り広げられていたんだというのがわかります。
時代が移り変わっても、使うツールが変化しても、やっていることは同じ。
歴史が今の自分たちと地続きの出来事なんだと感じられるのが、面白かったです。
清塚信也による、メインテーマ「熱情」の演奏
メインテーマは清塚信也さんによる、『ピアノ・ソナタ第23番「熱情」第3楽章』です。
“神格化”と“素顔”のせめぎあいを、音楽でも体感できるかもしれません。
清塚信也さんといえば、ドラマ『のだめカンタービレ』で、玉木宏さん演じる千秋真一のピアノ演奏を吹き替えたことで有名になった方ですが、このドラマでベートーヴェンの交響曲第7番をちゃんと知った、という人も多いのではないかと思います。
この映画ではベートーヴェンのピアノ・ソナタを弾いているので、ピアニストなんだから当然かもしれませんが、ベートーヴェンに非常に縁のある方なんでしょうね。
「Mrs.GREEN APPLE」のキーボード奏者、藤澤涼架さんが出演している
これはファンの方には嬉しいのではないでしょうか。
音楽が密接に関係している映画に、キーボード奏者であり、幼少の頃からピアノを弾いていたという経歴を持つ藤澤さんが出演するというのは、なんというか“縁”を感じますね。
これが藤澤さんの俳優・スクリーンデビューなんだそうです。
『#真相をお話しします』でボーカルの大森さんが映画デビューしたのに続く感じなのかな?
これからの俳優業に注目ですね。
※『#真相をお話しします』のネタバレ全開感想記事はこちら(未視聴の方は注意!)
ベートーヴェンファン必見のポイント
ベートーヴェンの“理想化”に共感してしまう瞬間
この映画では、実際のベートーヴェンは“小汚くてわがままなおっさん”として描かれています。
そんな彼であっても、音楽の才能は本物です。
才能に見合う、偉大な存在でいてほしい、いや、そうあるべきだ。
と考えてしまったシンドラーの気持ちが、少しわかってしまいます。
また、捏造の手段として使われた“会話帳の改ざん”についても、それをしてしまったシンドラーの気持ちが、ちょっとわかるような気がします。
あの誘惑は、耐え難いものがあるんじゃないでしょうか。
ベートーヴェン像が捏造だったとしても、音楽は揺るがない
伝記に書かれている内容に捏造があったとしても、ベートーヴェンの音楽そのものは本物で、何があっても揺るぎません。
あのエピソードってシンドラーの捏造なんだ、と残念に思ったとしても、ベートーヴェンの音楽が傷つくことはないのです。
当時も今も、ベートーヴェンの音楽は変わらず素晴らしいです。
古田新太の“小汚いわがままなおっさん”の魅力
古田新太さんが演じるベートヴェンは、まさに“小汚くてわがままなおっさん”なんですが、不思議と好感度が下がりません。
天才なんだから、こういう偏屈な面もあるだろう。
だけどチャーミングな一面もあるよね。
そんな感じで、憎めない人物として描かれています。
これは演者が古田新太さんだからこその、奇跡のキャスティングじゃないかと思います。
他の人だったら、単なる“嫌なやつ”になってしまっていたかもしれません。
この“小汚いおっさん”に、夢を見てしまったシンドラーの気持ちが、やっぱり少しわかってしまいます。
ベートーヴェンの音楽が好き(個人的な推しポイント)
私はベートーヴェンの音楽が大好きです。
特に好きなのが、交響曲第9番「合唱付き」です。
もっとも、この通称「第九」は、ほとんどの人が好きなんじゃないかなと思います。
ベートーヴェンといえば第九を連想する人も多いでしょう。
この交響曲第9番、私はじっと座って聴いていることができません。
聴いているうちに大興奮してきて、立ち上がってうろうろと歩き出し、踊り出し(?)、第4楽章に入ると、もうどたばた暴れ回りながら聴いています。
好きすぎて、じっとしていられないんですね。
コンサート会場の中継などを見るたびに、なんでみんなおとなしく座って聴いていられるの!? と思います。
第九もだけど、第七もそうですよね。
第七のサビ(?)なんか、走り出してしまいます。
多分、指揮をしたくなってるんじゃないかなーと思います。
なんていうか、心躍るんですよね。
ベートーヴェンの音楽は、心が踊るんですよ。
第九は私にとって、ある意味でロック……いや、シンフォニックメタルかな。
おとなしく座って聴いていることができないため、こんなに大好きなのに、コンサート会場で聴いたことがありません。
一生に一度は、コンサート会場でオーケストラの演奏と合唱を聴いてみたいです。
もっと歳をとって、暴れ回る体力がなくなって座っていられるようになったら、コンサート会場に行きたいと思います。
ベートーヴェン伝記の感動エピソード(第九初演)
そんな感じでベートーヴェンの音楽が好きな私は、当然のように伝記も読みました。
小学生のときに読んだので、内容をほぼ忘れていますが、すごく印象に残っているのは、第九の初演奏会のときのエピソードです。
オーケストラの指揮をしていたベートーヴェンは、観客に背を向けていた。
演奏が終了し、観客が万雷の拍手をするが、耳の聞こえないベートーヴェンはそれに気づかない。
オーケストラの一員に上着の袖をそっと引っ張られ、客席のほうを向くように促されたベートーヴェンが振り向くと、歓喜の涙を流している聴衆が盛大な拍手をしていた……
というものです。
これ、本当に素晴らしく胸を打つエピソードだと思います。
耳が聞こえないから観客の拍手に気づかないとか、楽団の一員にそっと促されて振り向くとか、振り向いたらスタンディングオベーション(?)で讃えられていることに気づくとか。
最高です。
このエピソードが捏造だったら?
かなりショックです。
しかしどうやら、これは「本当」らしいです。
これが実際にあったことだという描写が、映画の中にも出てきます。
こんなに美しい感じではなく、いろいろ裏話はありましたが、それでもほぼこの通りのエピソードです。
シンドラーは、ちゃんと“事実”も伝えているのです。
映画『ベートーヴェン捏造』まとめ|なぜ“捏造”したのかは劇場で
シンドラーの行った捏造というのは、「嘘で塗り固めた」というよりも、「事実をちょっと盛った」「盛り上がりそうな、いかにもなエピソードを付け加えた」という感じだったようだというのが、この映画を見るとわかります。
とはいえ、話を盛っちゃダメですよね。
しかも、その盛った話が、“事実”として後世に伝わってしまったのだから、シンドラーのやったことは重大な犯罪だと言えるかもしれません。
公文書偽造みたいなものです。
でもシンドラーは、その場しのぎの嘘や、適当なホラを吹いたのではありません。
“後世に伝わるように”、神格化されたベートーヴェン像を作り出したのです。
彼は、後世の人々に、「ベートーヴェンとは、かくも高潔で神聖な作曲家である」と伝えたかったのです。
シンドラーはなぜ、“小汚くてわがままなおっさん”であるベートーヴェンを、偉大な巨人のように見せようとしたのか?
まあ、そんな小細工をしなくても、ベートーヴェンが音楽において偉大な巨人であることは紛れもない事実なんですが。
だけどシンドラーは、音楽の歴史における業績だけではなく、ベートーヴェンという人物そのものを、“偉大な巨人”に仕立て上げようとした。
その動機がなんだったのか。
なぜ彼はそんなことをしたのか。
ぜひ、映画をご覧になり、確かめてみてください。
歴史ノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』の紹介
著者:かげはら史帆
書名:『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(河出文庫)
内容:ベートーヴェンの秘書であったシンドラーが、耳の聞こえないベートーヴェンとの筆談用ノートである“会話帳”を改ざんすることにより、ベートーヴェンの伝記や、世間で信じられているベートーヴェン像を捏造したという、「会話帳改ざん事件」の真相を追うノンフィクションです。
シンドラーがなぜそのような行動を取ったのかを、彼の生い立ちや時代背景、心理に迫りつつ紐解いていっており、ノンフィクションだけど小説を読んでいるかのような臨場感があります。
また、その結果ベートーヴェンの伝記がどのように作られ、信じられてきたのかを丁寧に考察しています。
「歴史の定説と思っていたことがくつがえされる」ため、謎解きミステリーのような趣もあって、とても興味深い内容となっています。
面白いので、ぜひ原作も読んでみてください。
【楽天ブックス】
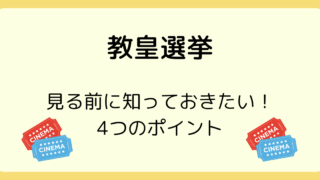
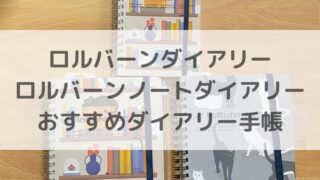

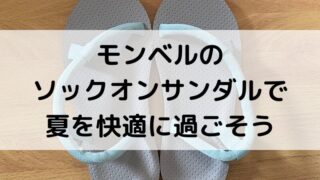
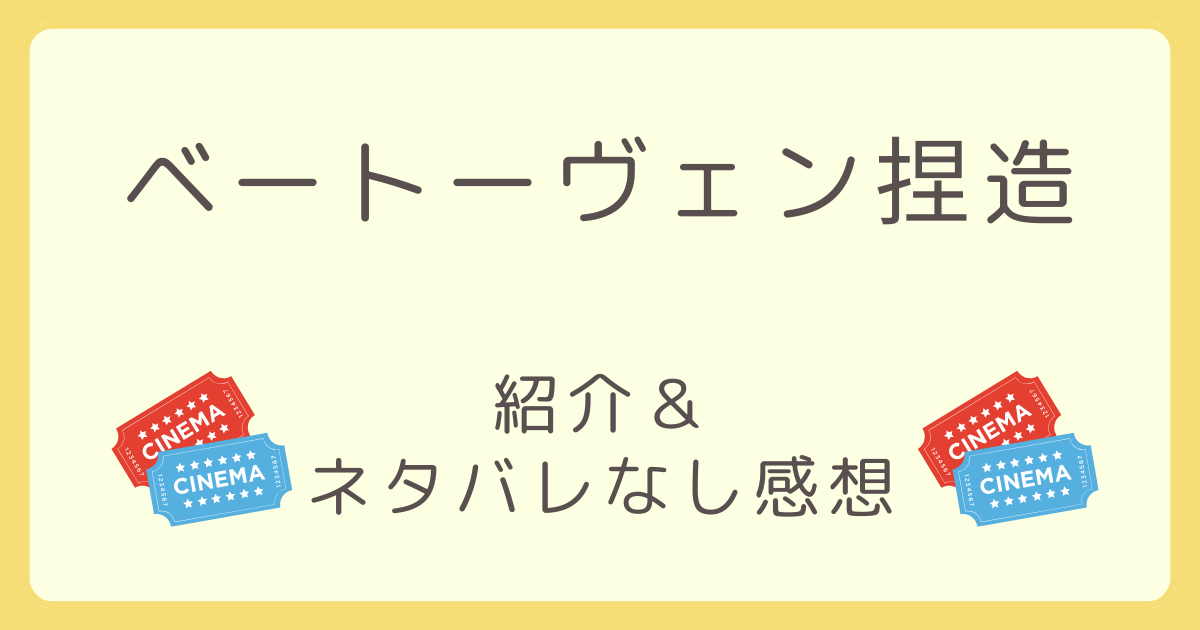
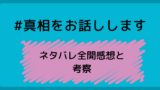
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/452cef12.309f5696.452cef13.2910ac69/?me_id=1213310&item_id=21070538&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0158%2F9784309420158_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

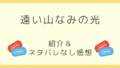
コメント